アンベール城から渋滞をなんとか抜けて次に訪れたのはジャンタル・マンタルです。
ジャンタル・マンタルとは「計測する機器」との意味で、ここでは天文観測所のことです。
インドの各地にジャンタル・マンタルはありますが、中でもジャイプールのものが最大級です。
扉は日時計で、太陽高度が高い夏用です。
反対側には冬用の日時計があります。
ちょうど両者が切り替わる春分・秋分の日だけはどちらも使えなくなります。
こちらは形状の異なる日時計です。
目盛りが細かく刻まれており、20秒の精度で時刻を知ることができます。
ただし、この時計はジャイプールの時刻を示しており、現在のインドの標準時とは30分弱のずれがあります。
形が面白く、最も興味深い機器でしたが、最後まで使い方はわかりませんでしたw
太陽の通り道や、星の運行を観測し、その予測結果から、占いなどに利用されていたそうです。
扉とは違う日時計と同じ形状をしています。
12個の機器が配置されており、それぞれ黄道十二星座の位置を知るためのものです。
一年の中で、今どの星座が太陽の位置にあるかを知ることができるようです。
これは山羊座用です。
みなさんくつろいでおりますが、公園ではありません。世界遺産ですw
ハノイのタンロン遺跡もまるで公園だったなぁw
でもまぁ、世界遺産で観光地なわけで、たくさんの旅行客がこうして記念写真を撮っておりました。
人がいなくなるのを待っていたんだけどなぁ…w
これは一番大きな日時計です。
これが作られた当時、機器は大きいほど正確に計れると考えられていたそうで、とにかくでっかく作られていますw
正確さ云々の前に、インド人はそもそもでかいもの好きな気がしますw
これは太陽や月の運行を観測する機器のようです。
例によって使い方はよくわかりませんw
![『Nari Valaya Yantra』 [15 mm 1-1500 秒 (f - 11) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/494da5e4558176d16d176fb327d8278a-364x550.jpg)
![『冬用』[15 mm 1-250 秒 (f - 5.6) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/1c192198cc320d72052b4ddf4707cbb6-364x550.jpg)
![『Laghu Samrat Yantra』 [15 mm 1-1500 秒 (f - 5.6) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/40914f4e09a946a599a560e4f23d7c00-550x364.jpg)
![『Jai Prakash Yantra』 [10 mm 1-1500 秒 (f - 4.0) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/eb9b2f35b5505355c5c238bb970e37e6-550x364.jpg)
![『Rashi Valaya Yantra』 [15 mm 1-3000 秒 (f - 11) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/fa8a0587db4a77b9da16f5099495237e-364x550.jpg)
![『山羊座』 [15 mm 1-1500 秒 (f - 5.6) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/475bf92a3c359d89d1e81baec9a65ac3-364x550.jpg)
![『公園のよう』 [15 mm 1-500 秒 (f - 5.6) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/2108e200bb3e94fb8bd4dbadc5574e2f-550x364.jpg)
![『思い思い』 [15 mm 1-1500 秒 (f - 5.6) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/bd56c664097d68851c954902f81d2c0b-550x364.jpg)
![『Samrat Yantra』 [15 mm 1-1000 秒 (f - 5.6) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/ed72c3a3f43fdf329439c0424494a7a3-550x364.jpg)
![『Ram Yantra』 [15 mm 1-6000 秒 (f - 11) ISO 160]](http://tsww.atelierask.net/wp-content/uploads/2016/01/1d6b388931892d2e88fe1e487bae39ff-550x366.jpg)
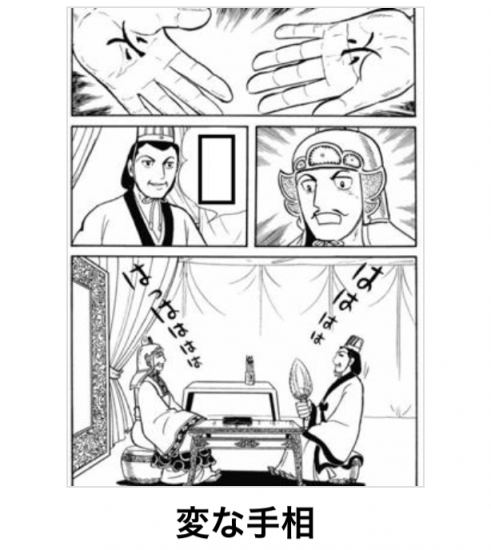






これはまた興味深い建造物ですね。
こういうのは見てみたいなぁ
いつ頃のものなんでしょう。
インドにはいい被写体いっぱいありますよ。
問題はそのための障害が多いということですがw
1728年に作られ、1901年に修復されたものが現存しているそうです。
おはようございます(^^
地上から星や太陽を観察していただけで、自転とか公転とかを感じれたというのが本当に不思議に思うんですよね。
目立つ星を繋げた星座が時期によって見えたり見えなかったりとか、太陽の季節によっての角度などを記録していって見えてきたものでしょうけど、長い年月を掛けての集大成がこの建物と思うと、そんなところにロマンを感じます。
もっと小さく作っても良かったのにw、と思うのは私だけでしょうか。
昔の人は今の気象予報のような技術はありませんでしたから、とにかく観測可能なものを駆使して、食糧確保に知恵を絞った結果なのではないかと思っています。
とはいえ、太陽や星の運行を観察しただけで時間・季節・方角・星の運行を把握できたというのはやはりすごいことです。
私の認識は「オリオンは冬の星座」ということぐらいですw
インド人は大きいものが好きなんですよw
大きい方が分解能が上がるので精度も確かに良くなるのでしょうけども、個人的には大きく作るための口実であったように思えてなりませんw
こんにちは
ご無沙汰しています。
18世紀の天文技術、かなり精緻なものですね。
20秒の精度で時刻が判る日時計なんて、凄すぎます。
当時、天文学の知識の高さが窺えますよね。
大きいものや最先端の技術は、富と自身の勢力を誇示する役割もあり、当時は積極的にヒト・モノ・カネを投入したことでしょう。
その結果、こうした技術が進んだのだろうと思います。
技術的には現代の方がもちろん優れていますが、現代科学は知識がなくても使えることを考えると、当時の人たちの方が、人間としての能力は発揮していたように思いますw